1.無機塗料について知っておきたい基礎知識
では、無機塗料とはどんな塗料なのか、まずはその基礎知識についてせつしていきます。
1-1.無機塗料は無機物を主成分とした塗料

無機塗料とは、セラミックやケイ素などの無機物を主成分としており、寿命が長く、他の塗料と比較しても高い耐候性を誇る塗料です。無機物は紫外線などにさらされても劣化が起こりにくいという性質を持っており、この性質を塗料に取り入れたことで15年以上の高耐候性を実現しています。
外装用塗料の1番の課題であった「紫外線による塗膜の劣化」を解決するために開発されたという背景があります。
1-2.無機塗料と有機塗料の性能の違いを知ろう!

先にも述べたとおり、塗料の種類の大多数を占めているのは「有機塗料」と呼ばれるもので、「無機塗料」はまだ種類が少なく聞きなれないということもあるかもしれません。
では、無機塗料と有機塗料の1番の違いは何でしょうか?
それは、それぞれに使用されている「樹脂」にあります。
有機塗料は、石油などの有機物(炭素を含むもの)から成る樹脂を使用した塗料のことを指し、一般的な塗料のほとんどがこれに当たります。金額も安いものから高いものまで幅広い種類の塗料が存在します。
一方で、無機塗料は鉱物などの自然物(無機物:炭素を含まないもの)を主成分とした樹脂を使用しており、高い耐候性・低汚染性を備えています。その耐候性は約15年で、塗装することで紫外線を浴びても劣化しにくい耐候性の高い塗膜を形成することができます。
樹脂・・・塗膜を作る主成分で塗膜の基本性能は樹脂によって左右される。
1-3.無機塗料と有機塗料はどっちがいいの?
では、無機塗料と有機塗料はどちらが優れているのでしょうか?
それぞれのメリットとデメリットを見ていきましょう。
【無機塗料と有機塗料の比較】
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 無機塗料 | ・耐候性が高い・不燃性がある
・カビや苔が発生しにくい |
・他の塗料より価格が高い・ひび割れしやすい |
| 有機塗料 | ・ひび割れに強い・価格帯が幅広い | ・紫外線の影響を受けやすい・耐火性が低い |
【無機塗料】のメリットとデメリット
<無機塗料のメリット>
①耐候性が高い
無機塗料の最大のメリットとして、15年以上の高い耐候性が挙げられます。無機成分を主としているため、雨や紫外線などにあまり影響されないため、外壁表面を長期間に渡って保護することが可能です。
②不燃性がある
主成分が炭素を含まない無機成分で構成されているため、有機塗料と比較すると火事の際などにも燃えづらいという利点があります。万が一の隣家の火事の際などにも、この不燃性によって二次災害の確率を低くすることが期待できます。
③カビ・苔が発生しにくい
カビ・苔の栄養分である有機物の含有量が少ないため、それらが発生しにくいという利点があります。
苔は、単に美観を損なうだけではありません。苔の根から発生する「根酸」という酸性物質により、本来アルカリ性であるスレート瓦が酸化することで素材自体の耐候性を低下させる恐れがあります。
<無機塗料のデメリット>
①他の塗料より価格が高い
無機塗料は、塗料の中でも耐候性やの面で機能性が高いが、施工の際は値段が高くなります。
②ひび割れしやすい
無機塗料は主成分が無機物で構成されているため、有機塗料と比較すると塗膜が硬いという特徴があります。
建物の外壁表面にひびが入った場合、一緒に無機塗料で形成された塗膜もひび割れを起こしてしまうことがあります。
外壁を塗装する場合は、有機塗料の伸縮性を活かすことをオススメします。

塗膜のひび割れ
【有機塗料】のメリットとデメリット
<有機塗料のメリット>
①ひび割れに強い
有機塗料の利点として、ある程度の伸縮性があることが挙げられます。
建物は振動などの外的要因によって常に少し揺れており、その揺れによって外壁表面にひび割れが発生することがあります。
有機塗料は伸縮性があるため、外壁表面にひびが入っても、一緒に塗膜にまでひびが入るリスクを低くすることができます。
塗装の一番重要な役割である「防水」の機能を果たすためには、外壁は有機塗料で施工するのがオススメです。
②価格帯が幅広い
有機塗料は無機塗料と比較して、各塗料メーカーごとにラインナップが豊富です。
その分、様々な価格帯が揃っているため幅広い塗料の選定が可能となっています。
<有機塗料のデメリット>
①紫外線の影響を受けやすい
有機塗料は太陽の紫外線にさらされることで、塗膜の劣化が目立つようになります。
紫外線の光を浴びることで、塗膜の結合が分解され、塗料の構成成分である顔料が表面に浮き出る「チョーキング」現象が発生します。
また、屋根は建物の中で最も紫外線を浴びる場所なので、無機塗料で塗装すれば紫外線の影響を受けにくいという特性を存分に発揮できるでしょう。
②耐火性が低い
有機塗料の主成分は石油・石炭からなる有機物なので、炎に弱いという弱点があります。
隣家の火事の際には、無機塗料と比較して炎が燃え移りやすく、二次災害に繋がる可能性が高くなります。
このように、双方にメリット・デメリットがあります。高コストでも長持ちさせたい方は無機塗料を、コストを抑えて塗装したいという方は有機塗料を選択するとよいでしょう。オススメの方法としては、劣化が進行しやすい屋根に無機塗料を使用し、外壁には有機塗料を使用するという組み合わせです。
1-4.代表的な無機系塗料を紹介
無機塗料の特徴を解説したところで、日本の代表的なメーカーから販売されている無機塗料をご紹介します。
・アプラウドシェラスター:日本ペイント株式会社
日本の塗料メーカーの大手、日本ペイントから発売の超耐候性・超低汚染性を有する水性有機無機複合2液型塗料です。
フッ素樹脂を超える有機塗料と無機塗料の2つのメリットを併せ持つ建物をより長く保護する為に開発された、日本ペイントの最高級塗料の一つです。
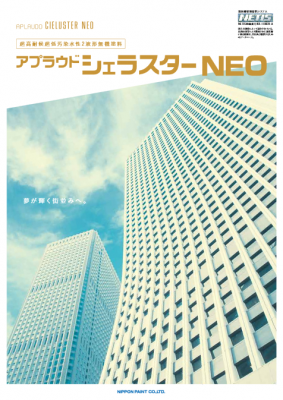
・アレスシルクウォール:関西ペイント株式会社
同じく大手メーカーの関西ペイントから発売の水性1液型無機系塗料です。
強靭で伸びやすい塗膜を形成し、無機成分を含みながらも、微弾性系下塗りや弾性系下塗りなど幅広い下地選択性と旧塗膜選択性を持つのが特長です。

・無機ハイブリッドコートJY:株式会社アステックペイントジャパン

アステックペイントジャパンの弱溶剤形二液屋根用変性無機系上塗材です。耐用年数20年以上を誇る「超耐候型」塗料で、低汚染性も持ち合わせ、多くの優れた機能を有する塗料です。
2.無機塗料の一般的な施工金額
他の塗料と比較した無機塗料の施工金額は下記の表のようになっています。
| 屋根塗装 | アクリル | 700~1,000円 |
| ウレタン | 1,500~1,700円 | |
| シリコン | 1,800~2,000円 | |
| フッ素 | 3,500~4,500円 | |
| 無機 | 3,500~4,500円 | |
| 外壁塗装 | アクリル | 1,000~1,200円 |
| ウレタン | 1,800~2,000円 | |
| シリコン | 2,500~3,500円 | |
| フッ素 | 3,500~4,500円 | |
| 無機 | 5,000~5,500円 |
※金額は近年の物価高による価格変動や、使用する塗料や業者、状況によって異なります。
表を見てわかるように、無機塗料の施工金額は屋根・外壁ともに他の塗料より高くなっています。
※無機塗料以外の塗料の特徴については、下記の表をご参照ください。
| 塗料 | 特徴 |
|---|---|
| アクリル | アクリル樹脂を主成分とする塗料。耐候性に乏しく現在はほとんど使用されていない。 |
| ウレタン | ウレタン樹脂を主成分とする塗料。価格と耐候性のバランスが良く、現在も木部塗装などに使用されている。 |
| シリコン | シリコン樹脂を主成分とする塗料。コストパフォーマンスが良く、現在の戸建塗装において最もポピュラーな塗料。 |
| フッ素 | フッ素樹脂を主成分とする塗料。コストは高いがシリコン塗料と比較しても耐候性に優れる。 |
3.無機塗料に関する留意点
無機塗料について解説をしてきましたが、1-2で挙げたデメリット以外にもいくつか留意すべき点がありますので紹介します。
3-1.高い耐候性を発揮するには職人の技術が必要
無機塗料に限ったことではありませんが、塗装をするには一定の技術が必要です。
耐候性を高めるためには、汚れや旧塗料を除去し、新しい塗料を均等な厚さに塗っていく必要があります。
特に、無機塗料のように耐候性の高い塗料の場合は、一定の厚さに塗らなければ、その効果が十分に発揮されないこともあります。無機塗料を選択する場合は、依頼する業者に無機塗料で施工した実績があるのかをきちんと確認しましょう。
3-2.無機塗料の上からは再塗装ができない場合がある
無機塗料には塗膜表面に汚れが付着しにくいという特徴もあります。
そのため、再塗装する場合に新しい塗料と無機塗料で形成された旧塗膜がうまく密着せずに、早期の剥がれを引き起こす可能性があり、塗装ができない場合があります。頻繁に色を変えたい場所に塗装するのは向いていないかもしれないですね。
4.まとめ
これまで無機塗料のメリットやデメリット、特徴や施工金額まで解説しましたが、いかがだったでしょうか。
無機塗料は高い耐候性を持つ塗料で、紫外線による劣化が起こりにくいといういう利点がありますので、屋根塗装に採用すれば、その機能を存分に発揮できるでしょう。無機塗料の特性をしっかりと理解し、納得のいく塗料選びをしていきましょう。








